| |
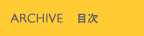
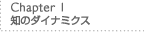 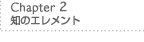
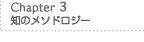 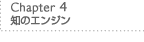 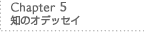 |
|
知識は人間と人間の間で交換され、行為を引き起こす。
言語哲学からグラフィックデザインまで
コミュニケーションのあり方を深く探るための8冊。
|
|
|
|
知識の哲学
戸田山和久 著
産業図書 2002年
ISBN4-7828-0208-0
現代の分析哲学における知識論の背景と展開について、類を見ない分かりやすさで解説しており、特に本文で紹介した「外在主義的知識論」について楽しく学べる。単なる教科書に終わらず、徹底した自然主義的知識論の展望も示し、刺激的である。(下嶋篤)
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
法隆寺を支えた木
NHKブックス 318
西岡常一/小原二郎 著
日本放送出版協会 1978年
ISBN4-14-001318-4
最後の宮大工といわれた西岡氏と建築学の小原千葉大教授という、木を扱ってきたプロと木の専門家の組み合わせによって木の知識を与えてくれる好書である。檜は材になってから200年は力学的強度を増すことなど、古代の宮大工の経験知の鋭さを指摘している。(本多卓也) |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
暗黙知の次元
言語から非言語へ
マイケル・ポラニー 著
佐藤敬三 訳
紀伊國屋書店 1980年
ISBN4-314-00301-4
ポラニーにとって「暗黙知」とは、余人が見落としてきた重要な問題に気づく能力である。解は手順を踏めば得られるが、解くに値する問題を見つけるのは難しい。大切なのは想像力であり、存在する物に対する想いである。端正な文章の背後にある詩情を感じ取りたい。(藤波努) |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
言語と行為
J・L・オースティン 著
坂本百大 訳
大修館書店 1978年
ISBN4-469-21072-2
著者は「話す」ということが、何かを描写することではなく、聞き手に命令したり、約束したり、説得したりすることだということを真正面から考えている。身近なテーマをここまで緻密に分析できることに驚かされる。翻訳も素晴らしく、原著よりも分かりやすい。(藤波努) |
|

|
 |
 |
 |
|
|
情報デザイン
わかりやすさの設計
情報デザインアソシエイツ 編
グラフィック社 2002年
ISBN4-7661-1290-3
国内外の「情報デザイン」の実践者と研究者によって書かれた論文・エッセイ集。このコンセプトのもとに行われているさまざまな学術的・実践的活動の躍動と多様さに触れるのに最良の書。本の構成も、さすがに情報デザインが行き届いており、面白い。(下嶋篤) |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
対話と知
談話の認知科学入門
茂呂雄二 編
新曜社 1997年
ISBN4-7885-0628-9
コミュニケーション研究の多様性を実感できる一冊。友人同士の会話からインタビューまで、多岐にわたる題材に対して、発話の音声言語的、社会・文化的な機能・役割、相互行為などの観点からの分析について、平易に説明されている。(石崎雅人) |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
図の体系
図的思考とその表現
出原栄一/吉田武夫/渥美浩章 著
日科技連 1986年
ISBN4-8171-6014-4
我々が何気なく使っている図的表現に関して、歴史的な経緯から始まり、図の分類、図の機能など網羅的、体系的にまとめられた労作である。一読、目からうろこが落ちる感激がある。(杉山公造)
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
コミュニケーションの自然誌
谷泰 編
新曜社 1997年
ISBN4-7885-0586-X
コミュニケーションの本質へと迫ろうとする刺激的な論考集。アフリカ狩猟採集民やサルのコミュニケーションから、電子ネットワーク上のコミュニケーションまで多岐にわたる題材を使い、関連性理論、会話分析などの基礎となる理論の知見を批判的に捉え、発展させようとしている。(石崎雅人) |
|
 |
 |
 |
 |
|
|









